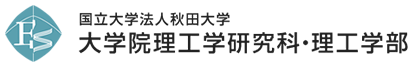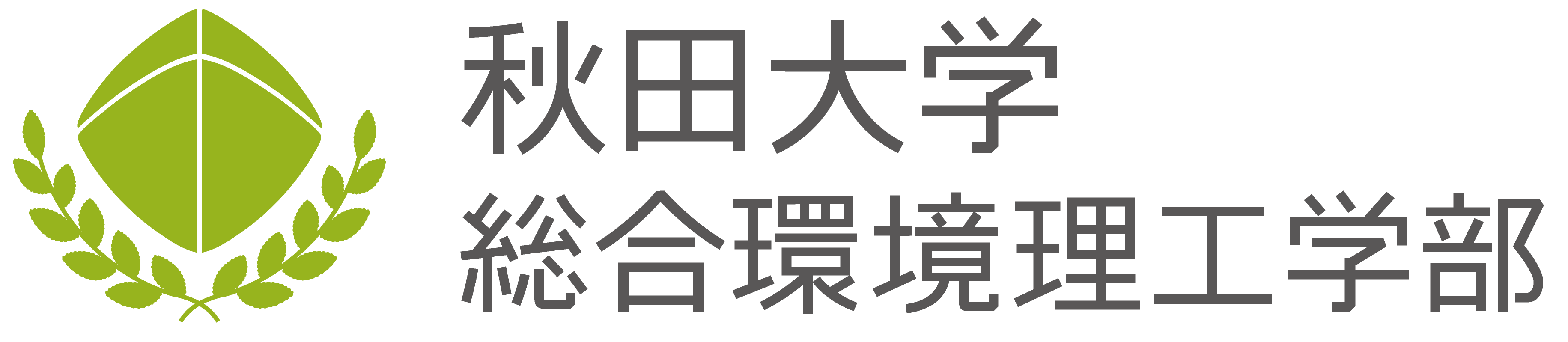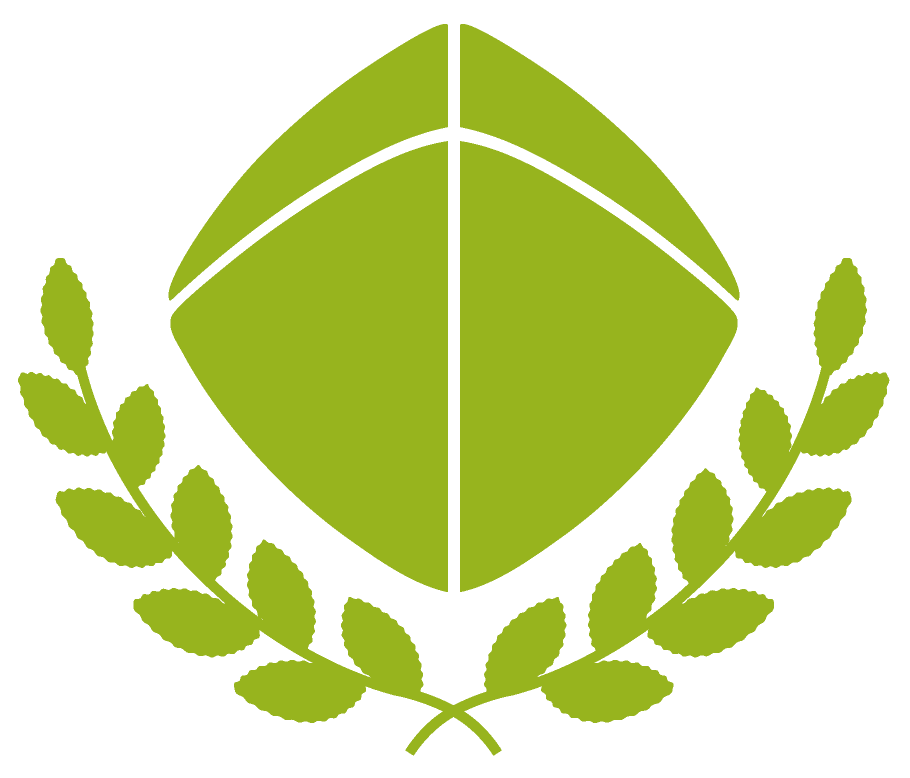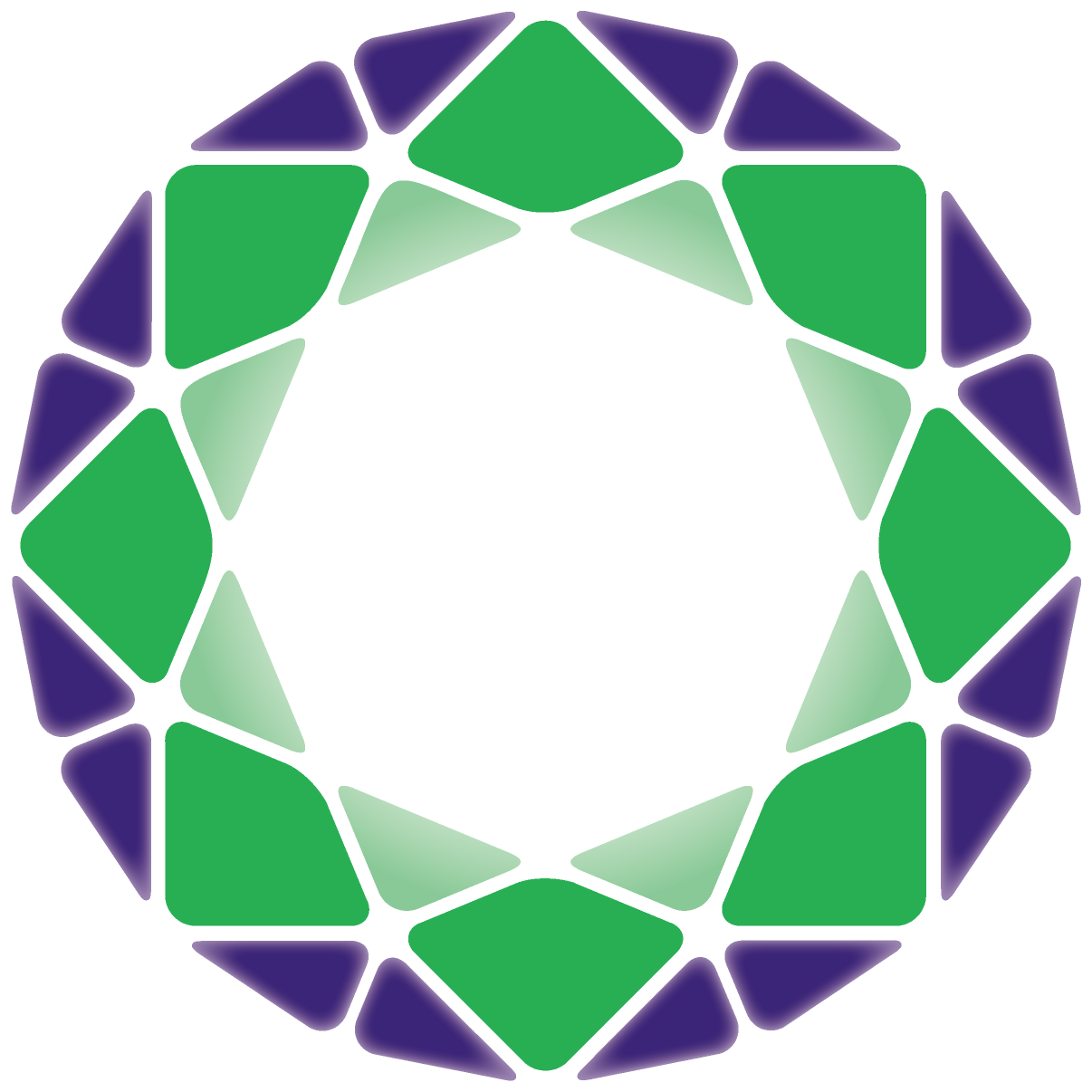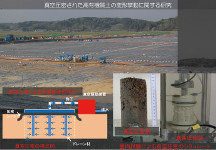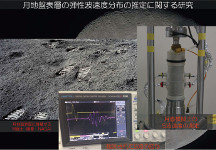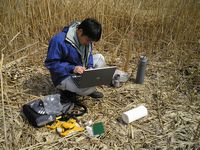コースの概要
土木環境工学コースでは、自然環境・社会環境に配慮した社会基盤の整備・維持・管理や安全・安心・快適な地域環境の創造・保全についての教育研究を行います。構造力学、建設材料学、土質工学、水理学、交通システム計画などを中心として、安全・安心・快適な地域環境を創造・保全する技術について学びます。
コースの特徴
土木技術は「自然の偉大な力の源泉を人類に役立たせるための技術」といわれています。公共施設の建設を通して、安全で快適な環境の創造により人間の生活環境の向上に貢献してきました。しかし、社会資本を整備するために現在の豊かな自然環境を破壊してよいとは限りません。土木環境工学コースでは5つの基礎的な分野における研究と教育をベースとして、災害に強く快適である持続可能な社会基盤の整備のあり方について学んでいきます。
どんな人材を育てるか
自然環境・社会環境に配慮した社会基盤の整備・維持・管理に関し技術提案ができ、培った技術を国内外に広く発信できる人材を育成します。
研究テーマ
環境構造工学分野
水環境工学分野
担当教員
地盤環境工学分野
土の性質や地盤の強度・変形に関する教育、そして泥炭性軟弱地盤の強度・変形問題から月面土の性質まで幅広い内容の研究を行っています。
福祉環境工学分野
高齢者や障がい者を含むすべての人々が快適かつ安心できる都市や道路、公共交通などに関する計画、自然環境との調和を目指した都市や交通の総合的な整備と運用に関する教育・研究を行っています。
環境材料工学分野
環境保全工学分野
環境保全に活用できる基礎情報の取得をめざして、フィールド解析に基づいた水資源を主体とした地域環境の理解に関する研究を行っています。